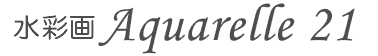
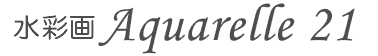
| 水彩画用紙の水張りの仕方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 私が教室で、普段やっている水張りの仕方を紹介します。 ただし、面倒くさい事が嫌いな私流のやり方なので、その点宜しくです(笑) 水張りは、最初はどうして良いか分らないので敬遠されがちですが、是非トライしてみてください意外に簡単ですよ。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まず、はじめに・・・なぜ水張りが必要なのか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 皆さんも経験があると思いますが・・・ 皆さんも経験があると思いますが・・・スケッチブックに絵を描いていて、広い面積に絵具を塗った時、紙がボコボコになり、谷間に絵具が溜まってしまいます。 これじゃ、良い仕上がりは期待できないですね〜! これが水張りが必要な理由! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紙がどれだけ延びるのか?・・・実験してみました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
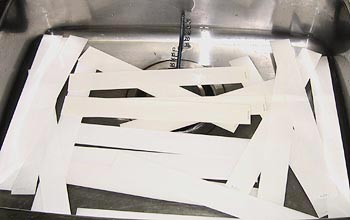 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラングトン300g/m2 アルシュ300g/m2 マルマン・コットマン230g/m2を、揃えて330mmの長さにカット。→ |
次に→水温23℃の水に同時にひたし、5分、10分、20分、30分、60分の順で、それぞれの紙を水から出して長さを測った。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| では、水張りをはじめましょう! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 用意する物 用意する物 ・水彩紙(今回は約38x28cmの紙) ・パネル又はシナベニヤ板 ・水張りテープ ・幅広の刷毛 ・水を入れる容器(綺麗な水) ・ハサミ ・霧吹き ・布巾 ・スクレーパー だいたいこんな物で良いでしょう |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 テーブルの上にビニールクロス(100均にて購入)を広げます。 まず、紙の裏に水を霧吹きし、表を上に向けて置きます。 次に、表にも十分に霧吹きをして濡らします。 そのまま約15〜20分間待ちます(この待ち時間が重要です) 待っている間に紙が乾かないように、常にヒタヒタ位に濡らしておく。 この待ち時間は非常に大切、その間に紙が水分を吸って延びるのです。 【注意】この作業をシナベニヤ板、パネルの上で行ってはいけません。 流しのシンクに蓋をして水が溜められる方は、下の方法でどうぞ。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 教室で使う水彩紙を水張りする時は、一度に沢山張るので、流しの排水溝に蓋をして水を溜め、水彩紙を約20分浸けています。 教室で使う水彩紙を水張りする時は、一度に沢山張るので、流しの排水溝に蓋をして水を溜め、水彩紙を約20分浸けています。注意: 水の圧力が紙の一部分に当ることを避けるため、 浸けた後に、蛇口をひねって水を出さないようにします。 写真は・・・水張りをする直前に1枚吊るして水を切っています。 教室の生徒さんからの情報 いつも流しが使える訳ではないので、カー用品店で売っている、写真現像のバットのような物を買って使っているそうです。 調理用でも現像用でも、バットがあれば一番いいですね。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 流しの蓋の密閉度を良くする為に、ビニールの紐を巻いている。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紙が十分に延びたら・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 水張りテープは、待っている間に必要な長さに切っておきます。 水張りテープは、待っている間に必要な長さに切っておきます。紙を板に置く前に、紙を斜めに吊るして余分な水を切ります。 裏表に注意して、板の上に水彩紙を置きます。 水張りテープの裏面を刷毛で塗らして、板と水彩紙を貼って行きます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 水張りテープを張る時に、なるべく指が水彩紙に触れないようにしましょう。四辺とも、同じようにテープを貼っていきます。 水張りテープを張る時に、なるべく指が水彩紙に触れないようにしましょう。四辺とも、同じようにテープを貼っていきます。手の出演は生徒さんです(^^) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 貼り終わったら、表面の水分が無くなるまでは水平に置いておきます。 貼り終わったら、表面の水分が無くなるまでは水平に置いておきます。ある程度乾いたら立て掛けても大丈夫。 そのまま一昼夜くらいは乾かします。 是非、やってみてください! 紙がピーンと張って、気持ち良く絵が描けますよ(^^)/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *水張りした紙に絵を描いて完成したら、これも完全に乾くまで置いてから、カッターで切ってください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 板に残ったテープは、あらかじめ剥がしておきます。 板に残ったテープは、あらかじめ剥がしておきます。几帳面な方は、完全に剥がしましょう・・・ そうでない方も、ある程度は剥がしておきましょう(笑 おっと、忘れてました。 残ったテープを剥がす時に、下に載せている スクレーパーがあると便利ですよ! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 板に残った水張りテープを剥がすのに、スクレーパーがあると仕事がはかどります。 板に残った水張りテープを剥がすのに、スクレーパーがあると仕事がはかどります。左のスクレーパーは、どちらも105円ですが下の歯の付いた方が剥がしやすい。好みで決めてください(^^)/ 剥がし方は・・・残った水張りテープを刷毛かスポンジを使って水で濡らしておきます。暫く置いてから、スクレーパーで削り取って下さい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注意点など・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・水彩紙の裏表が分らなくなりそうな時は、角に小さく印を付けておきましょう。 ・水彩紙が濡れている間は、紙の表面に触らないようにしましょう。 ・指で強く押さえるなど、紙に圧力をかけてはいけません。持つ時は、紙の端を持つ事。 ・水張りした紙に描いていて、紙が浮くなどした場合は、紙を濡らす時間が短いなどです。 ・水張りテープは、湿気に弱いので、切ったら直ぐにビニール袋に入れて下さい。 ・たくさん張ると嵩張るので板を使っていますが、1〜2枚ならパネルが良いでしょう ・板は6ミリ厚のシナベニヤを使用 (版画用の板として画材店にもあります。・・・普通のベニヤはダメです) ・8号以上のサイズは必ずパネルを使用しましょう。・・・パネルは画材店にあります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 Feb. 2004・・・22 Jan. 2007一部更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水張りの仕方 | 描き方① | 私の使用画材(絵具・紙・筆) | パレット・増色 |
| マスキング技法のヒント | 水彩用野外イーゼル | 超小型軽量イーゼル |